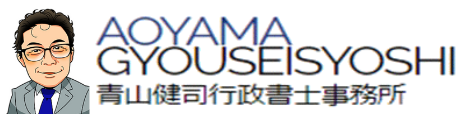あなたの会社の将来を守る『経営承継円滑化法による支援(事業承継税制、金融支援)』を考えてみましょう!
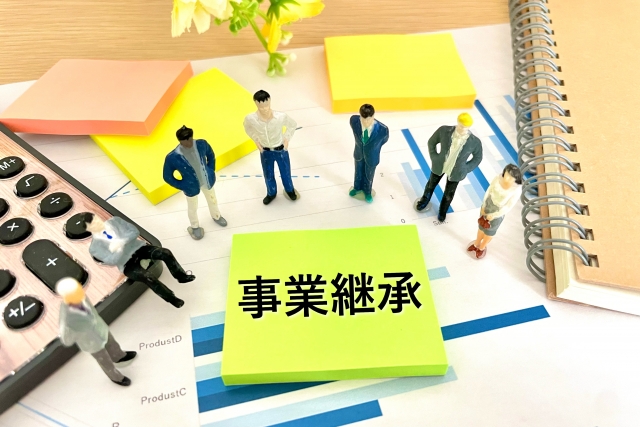
中小企業の事業承継は、近年ますます重要な課題となっています。
経営者の高齢化が進む一方で、後継者の確保や育成が十分に進んでいない現状が
浮き彫りとなっております。
事業承継における課題として、後継者への株式移転時に発生する
相続税や贈与税の納税資金の確保が、親族内承継の障害となる税負担の大きさや、
中小企業の経営者がM&Aに対して否定的な印象を持ち、
第三者への事業承継が進まない要因となるM&Aへの理解不足などが主な要因です。
今回は、そんな事業承継制度の一つである経営承継円滑化法による支援
(事業承継税制、金融支援)について説明してみたいと思います。
目次
- ○ 経営承継円滑化法による支援とはどんな支援でしょうか?
- ・税制面の優遇とはどんな内容でしょうか?
- ・金融支援とはどんな内容でしょうか?
- ・遺留分に関する特例とはどんな内容でしょうか?
- ○ 事業承継税制による支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の認定の具体的な流れを見て見ましょう!
- ・事前準備(後継者の決定と計画作成)
- ・経済産業省(都道府県)への申請(事業承継計画の提出)
- ・贈与または相続の発生
- ・税務署へ納税猶予の申請
- ・5年間の継続報告
- ○ 経営承継円滑化法による金融支援 〜信用保証の特例(保証協会の支援)〜
- ・どんな支援があるのでしょうか?
- ・どんなメリットがあるのでしょうか?
- ・どんなケースが対象になりますか?
- ・申請方法を見てみましょう!
- ○ 経営承継円滑化法による金融支援 〜日本政策金融公庫などの低利融資〜
- ・どんな支援があるのでしょうか?
- ・どんなメリットがあるのでしょうか?
- ・申請方法を見てみましょう!
- ○ 経営承継円滑化法による「遺留分に関する特例」の流れ
- ・事前準備(後継者と相続人の合意)
- ・都道府県の認定を受ける(経済産業局への申請)
- ・相続発生後、遺留分の請求が制限される
- ○ まとめ
- ○ 青山健司行政書士事務所では、行政手続・書類作成等をサポートいたします!
経営承継円滑化法による支援とはどんな支援でしょうか?
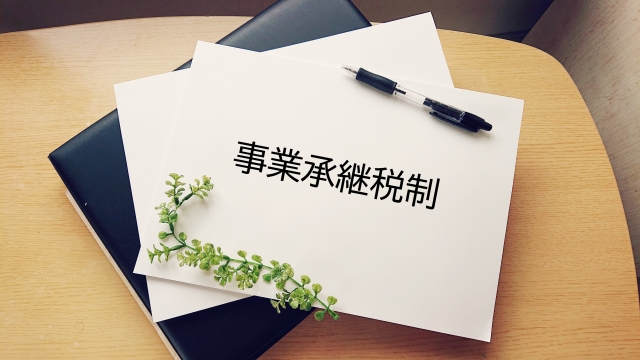
経営承継円滑化法は、中小企業の事業承継をスムーズに進めるために、
国が支援する制度です。
特に「後継者への株式の引き継ぎ」を円滑に行うための
①税制面の優遇、
②金融支援、
③遺留分に関する特例
の3つの支援があります。
事業承継の悩みの多くに、
・税金が高い…
・お金が足りない…
・相続トラブルが心配…
といった点が挙げられます。
そこで、この法律を使うとにより、
・税金の負担が軽くなる(相続税・贈与税の猶予)
・後継者が事業承継資金を借りやすくなる
・ 遺産相続トラブルを防いで、株式を後継者に集中できることができる
といったことが可能となります。
事業承継で悩んでいるなら、この制度を活用することで、
スムーズに会社を引き継ぐ可能性が高まってきます!
税制面の優遇とはどんな内容でしょうか?
税制面の優遇とは相続税・贈与税の負担を軽減することを目的としています。
通常、会社の株を親から子へ相続・贈与すると、多額の相続税・贈与税がかかります。
しかし、この法律を利用すると、税金の負担を大幅に軽減でき、
相続の場合 ⇒ 株式の 相続税が最大100%猶予(実質ゼロ)
贈与の場合 ⇒ 株式の 贈与税が最大100%猶予(実質ゼロ)
とすることができます。
但し、
会社が中小企業であること、
後継者が事業を継続すること
といった条件が必要となります。
このメリットは株式を後継者が引き継いでも、
税金の負担がほぼなくことになり、
経営がスムーズにできるようになります。
金融支援とはどんな内容でしょうか?
金融支援とは事業承継のための資金調達を支援することを目的としています。
事業承継のために後継者が会社の株式を買い取る資金が必要な場合、
低金利の融資を受けられる信用保証制度(保証協会が支援)によって、
借入時の保証を受けやすくなることが可能となります。
このメリットは、資金不足で承継が難しい場合でも、
国の支援でお金を借りやすくなるという点になります。
遺留分に関する特例とはどんな内容でしょうか?
遺留分に関する特例とは、相続トラブルを防ぐことを目的としています。
通常、亡くなった社長の子供や家族には『遺留分(最低限もらえる遺産)』があり、
株式が後継者だけに渡らない可能性があります。
この法律を使うと株式を後継者に集中させることが可能になり、
会社の経営が安定します。
このメリットは、遺産分割で『株を分ける』ことによる
経営混乱を防げるという点が挙げられます。
事業承継税制による支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の認定の具体的な流れを見て見ましょう!

経営承継円滑化法における支援措置のうち、
・事業承継税制による支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)のための認定
・金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)のための認定
・所在不明株主に関する会社法の特例のための認定
については、各都道府県が行っています。
具体的な流れについて確認していきましょう!
事前準備(後継者の決定と計画作成)
事前準備として、
事業を引き継ぐ後継者を決定
会社の経営状況を確認し、承継計画を作成
が必要となります。
ここで大事なことは、認定支援機関(税理士・会計士・商工会議所など)
に相談することをお勧めします。
経済産業省(都道府県)への申請(事業承継計画の提出)
事前準備が完了したら、『特例承認計画』 を作成し、
都道府県庁 に提出して、都道府県の認定 を受けましょう!
この認定を受けることにより、
税務署での申請が可能となります。
贈与または相続の発生
親または経営者から後継者へ株式を 贈与 または 相続 します。
その後、税務署へ「納税猶予・免除」の申請を行います。
「特例措置」を使うことにより、
株式の 贈与100%猶予、
相続税100%猶予(最終的に免除)
が可能となります。
税務署へ納税猶予の申請
株式の贈与・相続が完了したら、税務署に「納税猶予申請書」を提出します。
申請後、税務署の審査を受けて「納税猶予」が適用されます。
承継後5年間は事業継続が必須になります。
具体的には、従業員の雇用維持が条件となります。
5年間の継続報告
事業を続けることが条件となり、承継後5年間、
毎年税務署に「継続届出書」を提出します。
5年経営を続けると、最終的に相続税の免除が可能となります。
経営承継円滑化法による金融支援 〜信用保証の特例(保証協会の支援)〜

経営承継円滑化法における信用保証の特例は、事業承継時の資金調達を円滑にするために、
信用保証協会が通常よりも優遇された保証を提供する制度です。
わかりやすくいうと、代表者交代に伴う既存債務の借り換えや新たな資金調達を支援するため、
保証枠の拡大や保証料率の引き下げが適用される場合などがあります。
具体的な内容を見ていきましょう!
どんな支援があるのでしょうか?
後継者が事業を引き継ぐ際、株式の買い取りや事業資金の借入れが必要となります。
しかし、後継者が個人で銀行から融資を受けることは難しいことが多いです。
そこで、「信用保証協会」が保証人の代わりとなることにより、
銀行からの融資を受けやすくすることができる制度です。
どんなメリットがあるのでしょうか?
具体的なメリットについては、
借入がしやすくなる(保証協会が保証するため、銀行の審査が通りやすい)
信用保証料の負担が軽減される
といった点が挙げられます。
どんなケースが対象になりますか?
対象となるケースは
事業承継に伴い、後継者が会社の株式を買い取るための資金が必要
事業承継に伴い、設備投資や運転資金を借りたい
などが挙げられます。
申請方法を見てみましょう!
申請方法は以下の通りです。
①認定支援機関(商工会議所、税理士、金融機関)に相談
②都道府県の経済産業局で「経営承継円滑化法」の認定を受ける
③信用保証協会に保証の申請をする
④金融機関で融資を申し込む
⑤審査後、融資が実行される
「経営承継円滑化法」の認定については、
まずは都道府県庁や商工会議所に相談する事が大事です。
経営承継円滑化法による金融支援 〜日本政策金融公庫などの低利融資〜

経営承継円滑化法に基づく日本政策金融公庫の低利融資とは、
会社の事業を後継者にスムーズに引き継ぐための支援策の一つとして、
日本政策金融公庫が「低い金利でお金を貸してくれる制度」です。
具体的な内容を見ていきましょう!
どんな支援があるのでしょうか?
日本政策金融公庫(JFC)などの公的機関が、
事業承継のための資金を低金利で貸し出す支援です。
具体的には会社の後継者が事業を引き継ぐ際に、
必要な資金(株式の買取資金・事業承継に伴う運転資金・設備資金など)を
通常の融資よりも低い金利で借りれることにより、後継者の負担を軽減できる。
※ただし、条件:経営承継円滑化法の認定を受けることが要件となります。
要するに、
『後継者がスムーズに事業を引き継げるように、
公的機関が特別にお得なローンを提供してくれる制度』
と考えるとわかりやすいですね。
どんなメリットがあるのでしょうか?
具体的なメリットについては
一般の銀行より低金利で借りられる
長期間の返済が可能
担保や保証人の要件が緩和される
といった点が挙げられます。
申請方法を見てみましょう!
申請方法は、以下の流れとなります。
①認定支援機関(商工会議所・金融機関)に相談
②日本政策金融公庫に融資を申し込む
③必要書類を提出(事業計画書、決算書など)
④審査後、融資が実行される
「承継後の事業計画」が重要となります。
事前準備をしっかりとする必要がとても大事です。
経営承継円滑化法による「遺留分に関する特例」の流れ

『遺留分に関する特例』とは、事業承継の際に後継者へ株式を
集中させることを目的とした制度です。
通常、相続の際には遺留分(最低限の相続分)があるため、
後継者以外の相続人が株式を請求することができます。
これが原因で経営が不安定になることがあります。
しかし、この特例を使うと、相続人全員が合意すれば、
後継者が株式をスムーズに引き継げるようになります。
それでは、具体的な流れを確認していきましょう!
事前準備(後継者と相続人の合意)
事業承継を円滑に進めるため、後継者と他の相続人全員で話し合い、
遺留分の特例を利用することに合意します。
対象となる会社は非上場の中小企業(オーナー企業)で
会社の経営が継続されることが前提となり、
対象となる財産は会社の株式のみ(不動産や預金などは対象外)となります。
ポイントは、相続人全員の合意が必要であり、
誰か1人でも反対すると特例は適用できませんので注意が必要です。
都道府県の認定を受ける(経済産業局への申請)
次に、都道府県庁(経済産業局)へ申請し、「遺留分に関する特例の認定」を受けます。
提出する書類は
遺留分に関する合意契約書(公正証書)
後継者と他の相続人全員が合意したことを証明する書類
が必要となります。
なお、「公正証書」にする必要があるので、公証役場での手続きが必須となります。
また、会社の事業内容が分かる資料(定款・登記事項証明書など)も揃えて、
申請書(都道府県庁の様式)と一緒に提出します。
相続発生後、遺留分の請求が制限される
特例の認定を受けた後、経営者が亡くなっても、
他の相続人は遺留分を理由に株式を請求できなくなるため、
後継者が安心して経営を続けることができます。
この特例を使わない場合、遺留分をめぐる争いが起こり、
会社経営が混乱するリスクがあることも認識しましょう!
まとめ

中小企業の事業承継には、
後継者の選定と育成を早めに開始する『早期の準備』
相続税・贈与税の負担を軽減するための『税負担対策』
親族外・第三者承継の選択肢を広げる『M&Aの活用』
財務・業務の可視化と改善を進める『経営基盤の強化』
等が重要なポイントとなります
国も事業承継支援を重要課題と位置付け、ガイドラインの策定やM&A支援制度の整備など、
さまざまな施策に取り組んでいます。
士業やM&Aアドバイザーである専門家を活用して、
スムーズな承継を目指していただけると幸いです。
青山健司行政書士事務所では、行政手続・書類作成等をサポートいたします!
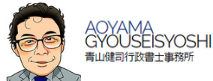
当事務所では、北海道札幌市及び道内で、
法人設立の手続き
起業のサポート
建設業をはじめとした
許認可申請の手続き
契約書作成などの
総合支援を行っております。
許認可・登録手続でお困りの方はもちろん、
設立に悩まれている方・経営に悩まれている方お気軽にご相談ください。
PROFILE

- 青山健司行政書士事務所 代表
-
事務所名:青山健司行政書士事務所
住所 :〒062-0932 北海道札幌市豊平区平岸2条11丁目3番14号 第一川崎ビル1階
TEL:011-815-5282
許可番号:行政書士登録番号15010797号
最新ブログ
- 2025年12月28日ブログ形だけの経営は通用しない‼『経営・管理』ビザ要件厳格化が示す、これからの外国人経営者像
- 2025年12月19日ブログ民泊開業の第一関門:消防法令適合通知書で整える“安全の基盤”
- 2025年12月19日許認可申請小さな会社でもできる!競争入札参加資格審査(物品・役務)ガイド
- 2025年11月21日ブログトラックがなくても物流事業はできる!第一種貨物利用運送で始めるスマート経営