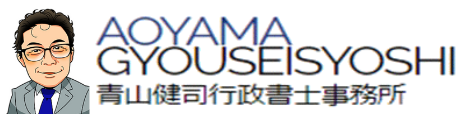インターンシップで「学び」と「労働」の違いは?補助作業はどこまでOK?
留学生インターンシップ(特定活動第9号)を受け入れる際、
「学びと労働の違いはどこ?」「現場の作業を手伝ってもらってもいい?」
という疑問をお持ちの企業は多いです。
札幌市内の企業から寄せられるインターンシップに関する疑問に、青山健司行政書士事務所の代表がお答えします。
「学び」と「労働」の線引きはどこ?
インターンシップは、留学生が「実務を通じて学ぶこと」を目的とした教育活動です。
「労働力」として扱うことは認められません。
教育目的として認められる条件
- インターンシップ契約の締結:企業と留学生の大学との間で正式な契約が必要
- 研修計画の作成:具体的な学習内容と時間配分を明記
- 指導担当者の配置:教育的な指導ができる体制を整える
NGな例:留学生が欠勤すると業務が成り立たない状態(事業運営に不可欠な労働力として扱う)
補助的作業はどこまで許される?
現場で補助的な作業を行うこと自体は問題ありませんが、以下の2点を守る必要があります。
- 経済的不可欠性がないこと:留学生がいないと業務が回らない状態はNG
- 常態的な反復作業でないこと:単純作業を指導なく繰り返し行わせるのはNG
補助的作業はあくまで「学習を深めるための手段」であり、労働力として使うものではありません。
研修計画書や指導記録で、教育目的であることを明確に示すことが重要です。
OK例とNG例
【OK】見学→一部実践→振り返りの流れで、指導担当者のもとで補助作業を体験
【NG】毎日同じ単純作業を繰り返し、指導やフィードバックがない状態
「責任ある作業」はどこまで任せられる?
品質検査、簡単な組立、接客補助など、ある程度の責任がある作業を体験させることも可能ですが、以下の原則を守ってください。
- 最終責任は企業が負う:学生のミスによる損害は企業側で対応
- 重要な最終判断を任せない:企業の信用・安全・金銭に関わる決定を学生に任せない
- リスク管理の徹底:指導担当者が必ずダブルチェックできる仕組みを設ける
これらを徹底することで、教育目的を確保しつつ、在留資格上の問題やリスクを最小限に抑えられます。
まとめ
インターンシップでは、「教育活動であること」が最優先です。
補助作業や責任ある作業を体験させることは可能ですが、
労働力として使わず、常に指導とフィードバックを伴う教育的な環境を整えることが大切です。
当事務所では、インターンシップの研修計画作成から在留資格申請まで丁寧にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
-
インターンシップの
教育目的と
作業範囲 -
学びと労働の違いは?補助作業はどこまでOK?
インターンシップは教育活動。補助作業は可能ですが、労働力として扱わず、指導体制を整えることが重要です。
関連ブログ
▶︎「人手不足」だけじゃない。学び合いの場としてのインターンシップ(特定活動第9号)とは?