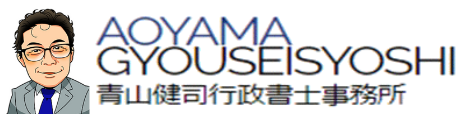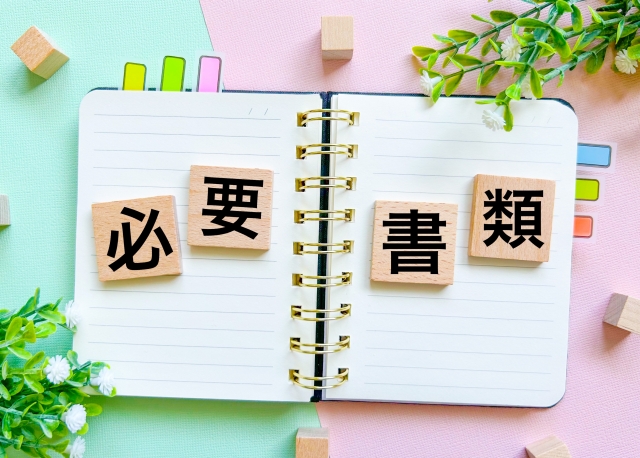
インターンシップの協定書はどう作る?大学が協力的でない時の対処法は?
留学生インターンシップを受け入れる際、
「協定書はどう作ればいい?」「大学がなかなか協力してくれない...」
という悩みをお持ちの企業は多いです。
札幌市内の企業から寄せられる協定書・書類作成に関する疑問に、
青山健司行政書士事務所の代表がお答えします。
研修計画と日報はどこまで詳しく書く?
入管から照会があった際の唯一の証明資料となるため、
研修計画書と日報は具体的かつ正確に記録することが必要です。
書類で示すべき内容
- 時間配分の証明:指導・見学・座学・振り返りが中心で、作業は補助的であることを明記
- 教育内容の証明:学生が何を学び、企業がどう指導したかが分かる記録
概要レベルではなく、日ごと・時間ごとの具体的な内容を記録しましょう。
協定書はどう作ればいい?
外国の大学との協定書を作成する際の主な注意点は以下の通りです。
協定書作成のポイント
- 署名と日付を必ず入れる:企業と大学それぞれの権限者が署名し、締結日を明記
- 労働を連想させる表現を避ける:「雇用」「賃金」「労働時間」は使わず、「研修」「実習」「指導」など教育活動の表現を使う
- ガイドラインを参照:出入国在留管理庁の告示・ガイドラインの「別添1」や「説明書」を基準に作成
英語で作成しても問題ありません。
ただし、入管への提出時には正確な日本語訳が必要です。
大学が協力的でない時はどうする?
現地大学の担当者が制度を知らず、なかなか書類にサインしてくれないケースは珍しくありません。
以下の対応策が有効です。
対応策1:説明の「再定義」と「単純化」
日本の複雑な制度説明は避け、「大学の承認が必要な短期研修用の確認書」であると伝えます。
- 学生の単位認定やキャリア形成に役立つことを強調
- 大学側の作業は「当社が作成した確認書へのサインのみ」と明確に
対応策2:書類の最適化と安心材料の提供
- 短時間で理解できる資料を用意
- 「労働」ではなく教育目的であることを示す補足資料を添付
対応策3:交渉経路の変更と上位者への働きかけ
担当者で進まない場合は、以下の方法を試しましょう。
- 国際交流部門・学術交流部門に相談
- 企業代表者名で学長・学部長宛に正式文書を送付し、上位判断を求める
- 学生本人から指導教員へ働きかけ:「このインターンが単位取得や卒業に必要」と伝えてもらう
まとめ
インターンシップの協定書は、教育活動であることを明確にし、労働を連想させる表現を避けることが重要です。
大学が協力的でない場合は、説明の仕方を工夫し、交渉ルートを変えることで進展するケースが多いです。
当事務所では、協定書の作成から大学との調整、在留資格申請まで丁寧にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
-
インターンシップ協定書と
書類作成 -
協定書の作り方と大学が協力しない時の対処法
研修計画・日報は具体的に記録。協定書は教育目的を明確に。大学が協力的でない時の対応策も解説します。
関連ブログ
▶︎「人手不足」だけじゃない。学び合いの場としてのインターンシップ(特定活動第9号)とは?